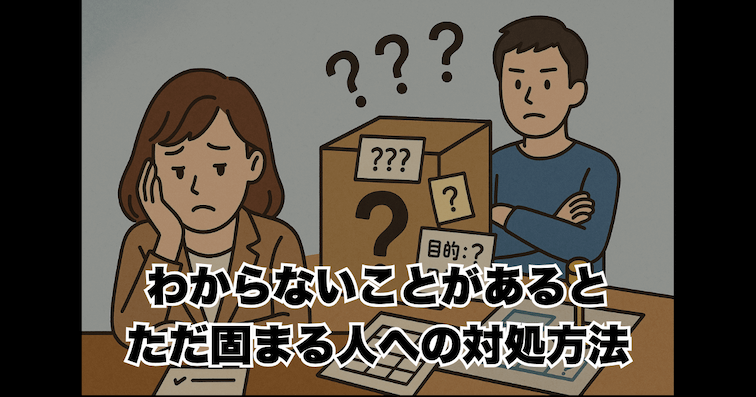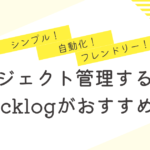目次
「言ったよね?」が口ぐせになってきたら、危険信号
「あの人、また止まってるんだけど…」
そう思った瞬間、もう結構ストレス溜まってますよね。
しかも、直接は言いにくい。だからSlackでやんわりコメントしてみたり、会話の流れでチラッと匂わせてみたり。でも伝わらない。伝わらないからまた同じことが起きる。
そうして気づけば——「え、なんで私が全部背負ってるの?」状態。“動かない誰か”よりも、「なんで誰も動かないのかを考えて疲れてる自分」に一番イライラしてたりします。
▶ 行動を取ってもらうための仕組みを作る: Backlog 30日無料体験(個人でもお試しOK)
“やらない人”が生まれるのは、その人の性格のせいじゃない
「動かない人が悪い」って思いがちだけど、実はほとんどの場合、その人が悪いわけじゃないんです。
だって、明日締切のタスクがあるなら、普通は動きます。でも、「やる理由がわからない」「いつまでか曖昧」「そもそも指示がざっくり」だと?そりゃあ、動きませんて。
動かない理由あるある3選
- タスクの目的や背景が共有されてない
→ 「なんでこれやるの?」が不明だと、やる気もスイッチ入らない。 - 締切や責任が曖昧
→ 「まぁ、まだいいか…」の無限ループに突入。 - 指示が抽象的すぎる
→ 「え、つまり何をどうすれば…?」ってなる。
人間、“やらないほうがラク”な状況に放り込まれたら、やらないんです。
でも逆に言えば、「やる理由」と「やるべき内容」がちゃんと伝わってれば動く。だから次は、“動く仕組み”の作り方、いきましょう。
タスクの目的がそのとき分からなくてもやらざるを得ない場面もあります。しかし、タスクの目的も言わずにやってくださいというだけの職場に居続けるかは……、よく考えた方がよいです。
「動く人」をつくるのは役職や立場じゃなく「動かざるを得ない」仕組み
「なんであの人には言わなくても動いてくれるのに…」って、つい比べてしまうこと、ありませんか?よく、動いてくれる人がいることは、運が良いことです。それが標準ではないことが多いです。でもそれ、相手の“センス”や“気配り力”じゃなくて、ちゃんと“動ける状態”をつくってあげてるかどうかの違いなんです。
ここでは、「あの人がまた止まってる…」を卒業するために、今すぐできる“動かす仕組みづくり”の3ステップをご紹介します。
①目的と期待値をちゃんと言葉にする
人は「なんのためにやるか」が腹落ちしてないと動けません。だから最初に伝えるのは、目的+ゴールのイメージです。
たとえば…
✗「営業資料つくって」
↓
◯「A社向けに絞った資料を3枚で、金曜の朝までに」
これだけで、動きやすさが全然違うんです。「どこに向かって、何をすればいいか」が明確になるから。
②誰が、いつまでにやるかを明示する
「●●さんが」「●●までに」「これをやる」。この3点セットがそろって、ようやく動けるタスクになります。
しかも、“名前を出す”のが超重要。気が引けている場合じゃありません。
「誰か」じゃなくて「◯◯さん」と名指しすることで、自分ごととして意識されやすくなります。
③コミュニケーションを“空気”にしない
「察してよ」は、事故のもと。どんなに気を使ってても、言葉にしなきゃ伝わりません。なので、やるべきはこの3つです。書く、残す、見えるようにする。「そんな話聞いてませんでした…」を防ぐためにも、仕組みの見える化は超大事です。
動かないのは“人の問題”じゃなくてタスク管理の“仕組みのスキマ”
ここまで読んで、「あれ?もしかして、悪いのって人じゃないのかも…」と思った方、正解です。
実際、「やらない人」って、ほとんどの場合“悪気ゼロ”です。むしろ、「どうしていいか分からなかった」「忘れてた」「そんな話だと思ってなかった」くらい。でも、それってつまり……
「仕組みにスキマがある」ってこと
人って、ちゃんと設計されたルールがあると安心するし、動きやすいんです。
- いつまでにやればいいか
- 何をどうすればいいか
- やった後どうなるか
このへんが決まっていないと、「今じゃなくてもいいか」と思える余地が生まれる=サボれる状態。逆に言えば、その余地をなくしてあげるだけで、人はちゃんと動くし、動かない人が目立たなくなります。
「誰が、何を、いつまでに」「誰が、何を、いつまでに」……、毎日タスク依頼時に呪文のように2週間言い続けていたら、さすがに身につきますよ。たった2週間で、この問題が永久解決するなら安いものです。
全部やった。それでも動かない人がいたら
ここまで読んで、目的も期限も伝えたし、ツールも使って見える化したし、全部やった。でも…やっぱり動かない人がいる。これ、あります。正直、あります。
対策A→でも、なんとかかんとか。対策B→でも、なんとかかんとか。以下、同文。
もう、なんにもするな。
手を尽くしたなら、それは「あなたのせい」じゃない
伝え方を工夫した。やる理由も具体的に伝えた。進捗が見えるようにもした。
それでも動かないなら、それはもう——
「仕組みの問題」じゃなくて、「相性の問題」かもしれません。
この場合、あなたが頑張りすぎる必要はないです。むしろ、「ミスマッチだった」と割り切って、“その人がいる前提で考えるのをやめる”ほうが、チーム全体が前に進めます。
仕組みは魔法じゃない。でも、努力した人を守る盾にはなる
どんなに丁寧に設計しても、100%動く人間関係はつくれません。でも、ここまで紹介したようなルールや仕組みがあると、「やらなかったのは、仕組みのせいじゃない」が明確になります。
つまり、責任が“やる側”にちゃんと返ってくる状態になる。
教育にも、仕組みにも限界があります。だからこそ、手を尽くしてダメなら、そこにこだわらず、次へいきましょう。
「動かない人問題」は、“人の質”じゃなく“動くしかない仕組み”の話
「あの人が悪い」「なんで私ばっかり」ってモヤモヤしたら、まず“動ける環境”があるかを疑ってみるのが、一番ラクな対処法です。
- 目的や背景がわかるか
- アウトプットが明確か
- 期限が決まってるか
- 進捗が見えるか
- コミュニケーションが残ってるか
このへんの仕組みが揃っていれば、多くの人はちゃんと動けるようになります。
でも、手を尽くしても動かない人がいたら?それはもう「仕組みの問題ではない」というサイン。“いないものとして考える”勇気を持って、次に進んでOKです。
察し文化から抜け出すと、みんなラクになる
怒るより、決める。イライラより、仕組みを整える。これだけで、空気読み合戦から一歩抜け出して、ちゃんと動くチーム、ちゃんと前に進む環境がつくれます。
「あの人また止まってる…」とため息つく前に、ぜひ、ひとつルールを置いてみてください。あなたが動かなくても、チームが動き出すかもしれません。