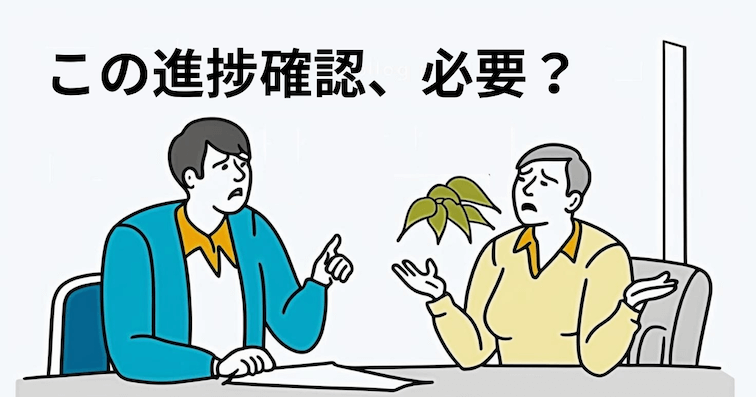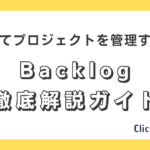目次
毎回「進捗どう?」って聞くの、地味にしんどくない?
「進捗どうなってますか?」
何気なく聞いてるこの一言、言う側もしんどいし、聞かれる側もプレッシャー。正直、毎回聞くのも気まずい。「また聞かなきゃいけないのか…」「なんか責めてるっぽく聞こえないかな…」とか思う。返事もお決まりの「今やってます」「進めてます」みたいな曖昧なやつ。それ、どのくらい進んでるの?ってなる。結局また聞くことになる。永遠ループ。
このやりとりの時間って意味あるの?もう、聞かなくても分かる状態にしたほうが早くない?
“進捗どう?”から解放されたいすべての人へ。この記事、捧げます。
「進捗どうですか?」を聞く状態になっていることに問題あり
実はこれ、「聞く側が悪い」わけじゃなくて、見えない設計が悪い。
以下の3つ、全部当てはまるなら要注意です。
- タスクの状態が見えていない
- 進捗の意味が人によって違う
- 情報が更新されていない
タスクの状態が見えていない
ToDoリストには「◯◯の準備」「資料作成中」とだけ書いてある。
でも、それが今どこまで進んでるのか?が分からない。
見えてないから、聞くしかない。
“進捗”の意味が人によって違う
- Aさん:「進行中です」=構想が頭に浮かんでる段階
- Bさん:「進行中です」=もう8割終わってる
同じ言葉なのに、中身が違いすぎる。
情報が更新されていない
前に聞いたときと、状態が一緒。
進んでないのか、進んだけど書き換えてないのか、分からない。
つまり、「進捗どう?」って聞くのは、“確認せざるを得ない状態”のサインなんです。
“聞かずに分かる”状態をつくる3つの仕組み
これさえ揃えば、進捗確認からほぼ卒業できます。
タスクに「進捗ステータス」をつける
まずは状態をささっと付けるだけでも効果絶大。
- 未着手(まだ見てもいない)
- 進行中(20%: 実際動き始めている、50%: 半分終了している、etc.)
- 完了
- 保留
タスクの横にこの状態がついてれば、誰がどこにいるか一発でわかる。ちなみに、“早く動く”だけで信頼される人になるテクもあります。
おすすめは、タスクを動かしたときに一緒にステータスも更新するルール。「1日1回だけ更新」でもOKです。
“進捗の定義”をチームで統一する
みんなの中で「進行中ってどのくらい?」が違うと、混乱します。たとえばこんな風にルール化しておくと、意味のズレが減る。
- 「進行中」=50%以上完了してる状態
- 「完了」=レビューまで済んでる
曖昧さを減らす=“聞かなくても分かる”への第一歩。
これがもう全てです。この定義と、関係者の認識合わせ、ステータスの更新ができればもう「進捗報告」なんて不要です見ればわかるから。
プロジェクト全体の“見える場所”を作る
カンバン/ガントチャート/タスクリストなど、形式は何でも良いです。大事なのは、全員が同じ場所で、同じ情報を見られる状態にすること。極力二重管理は避けること。
「進捗確認」の時間は一番ムダ、重要なのは遅れやリスクに対する議論
毎週の定例会議でよくある光景。メンバーが順番に話します。
「このタスクは…今やってまして…」
その口頭報告、必要ですか?その時に聞く必要ある?
「その進捗、会議の前に見えてたらよくない?」って話です。オンスケ報告はどうでもいい。それを聞いて、で?ってなるからです。
聞きたいのは、『進捗の遅れやリスクへの対策案』です。
テキストでタスクが定量的に見える状態があれば、会議はもっと建設的に使えます。
- どこが詰まってるか
- リスクがあるところはどこか
- どう改善するか?
対面でもオンラインのビデオ通話でも、『わざわざ人間が集まっている』のは、議論や結論を合意するためです。そのために時間を使えるのが理想です。そのため、「読むだけで伝わる仕事」にしておく状態は、チーム全体の生産性を底上げします。
「進捗報告だけ」の会議は、ビジネススキル不足とアピールしているのと同じ
会議には目的によってある程度その流れや期待状態が決まっています。
会議には目的ごとに、概ね次のような進行と期待状態があります。
① 説明会 :説明 → 質疑応答
② 情報収集 :説明 → フォーマット提示 → ヒアリング → 確認(洗い出しなど)
③ 意思決定 :
説明 → ブレスト → 判断基準の合意 → レーティング → 決定確認
課題オプションの比較 → 判断基準の合意 → レーティング → 決定確認
④ 問題解決 :問題の記述 → 原因分析(可視化) → 解決策検討 → ③と同じ流れ
⑤ 承認 :説明(情報不足なら差し戻し) → 質疑応答 → 承認/否認
そして目的に関係なく、会議は必ず“逆算”してスケジュールするのが鉄則です。
ここが押さえられていれば、あとは チーム全員のタスクを見える化 すれば勝ったも同然。
すでに「なんとなく会議」から卒業している人は、次はタスク管理を自動化してみませんか?
▶ Backlog 30日間 無料トライアル
「聞かずに分かる」は最強のマネジメント
- 聞かれる前に見せる=信頼される人
- 聞かないでも分かる=チームの空気が良くなる
- 見える化=会議時間が減る
進捗って、本来は「問い詰める」ものじゃなくて、自然と伝わってるものにしていくべきです。
Backlogの導入事例を整理した内容を見ると、多くの企業が、調整やら報告、会議などの間接業務から解放されて、成果に直結する業務に注力できています。
報告受ける側と報告する側と別れているのがそもそも問題です。何を話せばよいか分かっているなら、各自書いといて、全員で議論・方針合意取ろうで良いはずです。そのための設計を、いま仕込んでおく。
“進捗どう?”から卒業して、見える仕事スタイルに切り替えていきましょう!