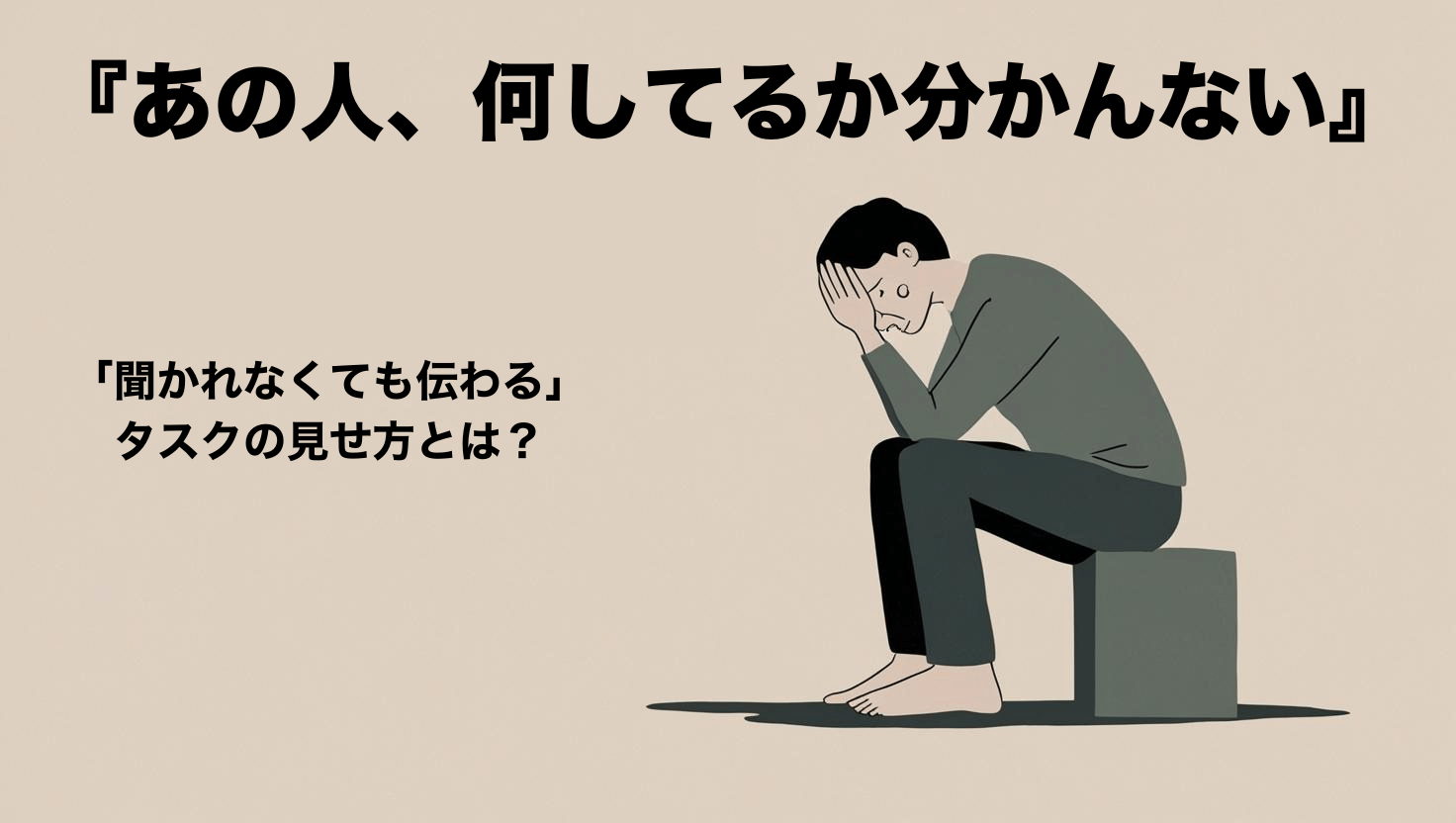目次
「『あの人、何してるか分からない』と言われる前に」
成果を出している“はず”なのに評価が伸びない。その原因の多くは 仕事の進み具合が周囲から見えない ことにあります。
たとえば、Kanbanを導入した複数のケーススタディでは、サイクルタイムが平均で約 20 %短縮し、スループットが向上したと報告されています。さらに、職場の透明性を高めた企業では 従業員エンゲージメントが 76 %高い という調査結果もあります。チーム文化の研究で知られる Google の Project Aristotle でも、心理的安全性が高いチームは経営層から“効果的”と評価される確率が約 2 倍 と示されています。
裏を返せば、どれほど多くのタスクをこなしても プロセスが閉ざされていれば信頼もリソースも集まりません。
可視化は「結果」だけでなく「途中経過」まで評価対象に引き上げる、最短で最強のレバレッジなのです。
“何してるか伝わる人”の共通点とは?【カンバン×ステータス】
可視化がうまい人は例外なく、タスクの状態を 3 秒で示す 仕組みを持っています。なぜ3秒で示せるかといえば、普段からタスクが可視化された仕組みで管理されているからです。
Backlog のカンバンボードは「未対応→処理中→完了」という基本列を中心に、独自のステータスを自由に増減でき、カードをドラッグするだけで状況が全員に伝わります。
重要なことは、以下です。
- 処理中の状態のタスクを2,3個に絞る
- タスクのステータスは3-5本に絞る
処理中の状態のタスクを2,3個に制限する
マルチタスクのように見える人は、実質シングルタスクに注力し、次から次へとタスクを終わらせています。
コツとしては、処理中のタスクの上限を設けることです。そうすることでどのタスクに注力するか制限がかかります。自ずとシングルタスクに集中できるようになります。
緊急の対応が発生しそちらのタスクを優先する場合は、処理中のタスクを未対応に戻し、緊急対応タスクを処理中に追加するとよいです。この更新追加作業は、優先順位付けによる結果ですね。
タスクのステータスを3-5本に絞る
今までの経験から、タスクの状態は、未対応、処理中、完了で十分です。この3つの状態は、職種やタスク内容によらず使えるステータスのためだからです。
カスタマーサポートの問い合わせ対応プロセスなどある程度フローが確立されている業務であれば、「問い合わせ」というタスクがどのように流れていっているか把握するために、タスクのステータスを独自に増やすのは問題ないです。しかし、普段の業務やプロジェクトのような都度タスクが発生するものについては、未対応、処理中、完了で事足ります。
よくあるタスク管理としては、「タスクの状態毎に管理する」「タスクの状態を増やさず、タスクのアクティビティを登録する」の2パターンがあるかと思います。以下で説明しますが、後者のパターンがおすすめです。
タスクの状態毎の列を追加する
タスクに対し、◯◯作成、◯◯のレビュー、◯◯レビュー指摘反映、再レビューなどの状態を追加する。タスクがそのステータスを順に動くようなイメージです。この方法は人によっては関係ないステータスもあるため、ノイズになるのです。
| ステータス | タスク |
|---|---|
| 未対応 | |
| 処理中 | Aタスク |
| レビュー | Bタスク |
| レビュー指摘反映 | |
| 再レビュー | |
| 再レビュー指摘反映 | Dタスク |
| 完了 | Cタスク |
状態を増やさず、タスクに対するアクティビティを増やす
タスクに対するアクションを登録して、未対応、処理中、完了で対応する。これで、タスクがまだ対応していないのか、対応中か、終わったのか明確に分かるんです。
| ステータス | タスク |
|---|---|
| 未対応 | Dタスク再レビュー指摘反映 |
| 処理中 | Aタスク作成 Bタスクレビュー |
| 完了 | Cタスクレビュー指摘反映 |
例えば、「Dタスク再レビュー指摘反映」というタスクを見てみます。『このタスクが1つ目のパターンでは対応中かどうか判別つかないこと』が分かりますか。
2つ目のパターンを見ると、「タスクとしてはあるけどまだ着手していない」ということが明確に分かるんです。
都度、タスクを登録するのは面倒に思うかもしれませんが、そこがBacklogだと登録タスクの負担が少ないため、ストレスなくタスクを登録できるんですね。
さらにBacklogではカンバンのようなボード機能やガントチャート機能上で課題カードを開かずにステータスだけ切り替えられるため、更新コストは 1 日 10 秒。タスク可視化が「続かない」最大要因は、更新が面倒になることです。
操作が軽い仕組みは、それだけで可視性を自動的に維持してくれます。
タスクを「見える化」するポイント【Backlog実例】
カンバンで現在地を共有
ステータス列は最小限、処理中のタスクは2〜3 件に制限する。
担当者アイコンにより「誰がなんのタスクを処理しているか」を一瞬で判別する。
ステータスは 3 段階で十分
未対応 / 処理中 / 完了 の3ステップで十分。ここを増やしすぎると更新が面倒になり、結局形骸化します。
ガントチャート+バーンダウンチャートで“全体像”を数字で示す
ガントチャートは期限超過タスクを赤帯で警告し、バーンダウンチャートは残作業量を日次でグラフ化します。
進捗線と理想線の乖離を見れば、会議の議題は自然に“リスク解消”へ集中します。
ガントチャートとは
横軸に時間、縦軸にタスクを並べた バー(帯)形式の工程表です。タスクの開始・終了日、長さ(期間)、依存関係を 1 画面で示せるため、プロジェクト全体の流れとクリティカルパスが直感的にわかります。
※Backlogでは依存関係まで分かりません。
主なメリット
- 進捗を“赤帯”などで警告し 遅延を即発見(Backlog も同機能)
- リソースが重複する箇所を視覚化し、 人員・工数の衝突を早期回避
バーンダウンチャートとは
縦軸に残作業量(タスク数など)、横軸に時間(1週間単位や1ヶ月単位)を置いた 折れ線グラフ。理想線と実績線の差で「予定より何 %進んでいるか/遅れているか」を瞬時に把握できる。
主なメリット
- 遅延やスコープ膨張を 早い段階で検知し、対策を打てる
- 進捗が線で見えるため、経営層・顧客との意思決定(工数↔機能のトレードオフ)が容易
- 「着地できるペース」をチームが学習し、作業負荷を平準化できる(燃え尽き防止)
頑張りは、見せなきゃ伝わらない
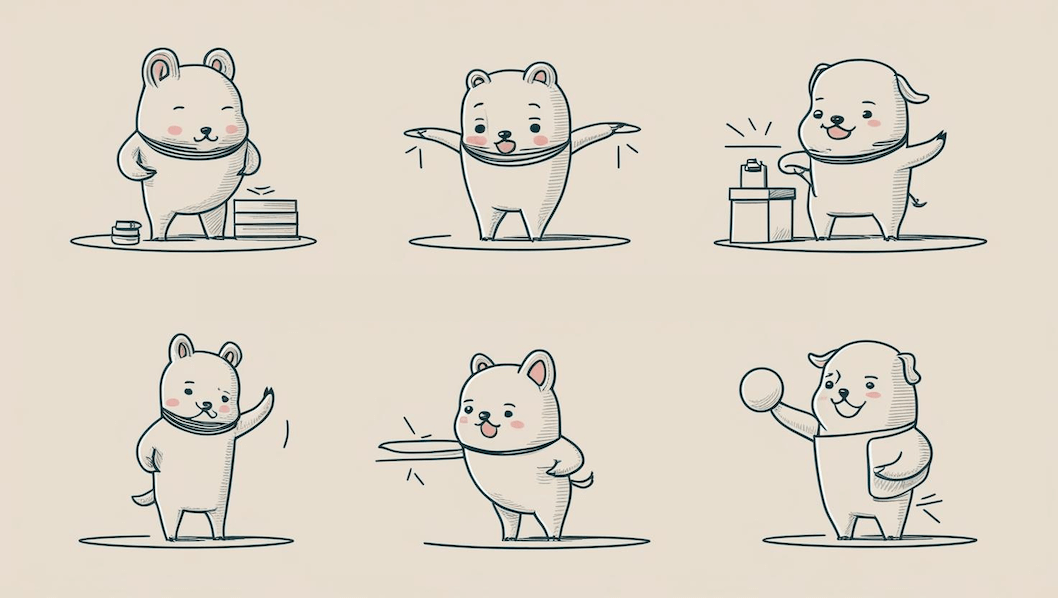
リモートワークが当たり前になり、上司や同僚があなたの作業を横目で見る機会は激減しました。
Forbes の HR 調査によれば、“透明性の高い仕事の進め方” は信頼と裁量を同時に引き上げる とされています。
カンバンとバーンダウンで “今どこ・どれだけ進んだか” を日次で共有すれば、「進捗どう?」というメッセージは自然に消え、成果につながる業務に専念できます。
余白を示せば助けも集まる
可視化の目的は「忙しさアピール」ではありません。ガントの空き帯やカンバンの「処理中」列が小さいほど、他メンバーが依頼しやすい余白が見えます。
互いのキャパシティがわかるとタスク融通が加速し、チームの総スループットは右肩上がりになります。
心理的安全性の専門家は、透明性と自己開示が高いほど「支援要請」が増え、成果が上がりやすいと指摘しています。
毎日の見える化が「信頼残高」を積み上げる
- 納期遵守率 が上がり、顧客からの追加発注を獲得
- マイクロマネジメントが不要 になり、裁量とリモート比率が向上
- 引き継ぎがスムーズ で、スキルローテが早まりキャリアが広がる
これらはすべて「仕事が毎日みえる」ことの副次効果です。
あなたのタスクを 1 枚のボードに置き、進捗線を 1 本のグラフで示すだけで、信頼は複利で蓄積されていきます。
まずは 3 枚のタスクだけ登録してみてください。
Backlog のカンバン・ガント・バーンダウンはすべて無料トライアルで体験できます。
▶︎ Backlog 30 日無料トライアル